タッピングタッチの集い
2022年4月2日(土)10~12時
9人の参加で、楽しい春の集いが開かれました。今回のファシリテーターは、愛知の渡辺英明さん。いつもの、まったりと穏やかな声で5ステップ腕だけ散歩で始まりました。
タッピングタッチの企画はどれも「ゆっくり、やさしく、ていねいに」が共通しているとは思いますが、講座や研修は学びが中心で、集いはゆる~くタッピングタッチを実践して、なんでも話せる場ともなっています。
今回は「この2年を経て、なんだか過剰適応しているのかも」という発言から、色々な意見がそのまま共有されて、いい時間となったように思います。安心して思いを話せる、理解してもらえる場は大切ですね。
以下、感想です。
*みなさんのご意見をいただけたこと、とても有意義でした。
いままでは誰かに話しても「そうだよねー、怖いよね」とか「気にしすぎなんじゃない?」という反応がほとんどだったので、段々自分の中にしまい込んでしまっていました。今回みなさんとシェアできた、それだけで気持ちが落ち着きました。自分の真ん中にすっと立っている、という実感が持てました。とても不思議です。
霧が晴れたというか、視野が開いた感じで、自分の進む方向が見えてきたような気がします。心も体も軽く4月が迎えられます。
*コロナ禍のお話を聞いて、知らず知らずのうちに自分が過剰に心配しがちになっているなと思いました。もっとリラックスしてできることをしていこうと思います。

*本日は、久しぶりに参加でき、皆さまともお目にかかれてとても温かいきもちになりました。解決ということにはならないところで私たちは生きているのだなという感覚と、静かな心持ちでいるという感じを、皆さまとご一緒に味わうことができたと思いました。
*忌憚ないディスカッションを聞いていて、様々な情報に晒されて、無意識のうちにストレスを溜めているのだなぁと思い、セルフケアの重要性を感じました。
*今日のテーマとしては、「コロナ禍、非平和的状況のなかで、私たちがタッピングタッチを実践していくことの意味」ということになったのかと理解しています。
「自分を信じ、人の中にある力を信じて、できることをして行く。」ということなのかなあという話になったのかとも。
 コロナ禍も2年になるのに、どうなっていくのか分からない状況の中で、「なんだかほんとに疲れるね~疲れたね~。もうこんな風にポストコロナを待っとったんでわ、いつになるか分からんよね。待っとるだけでは、振り回されて、あかんようになってくわ。もうそろそろ自分たちの手にコントロールを取り戻して、元気でおらんと、あかんわ!!」と、四日市弁ばりばりで友人と話したのが11月でした。
コロナ禍も2年になるのに、どうなっていくのか分からない状況の中で、「なんだかほんとに疲れるね~疲れたね~。もうこんな風にポストコロナを待っとったんでわ、いつになるか分からんよね。待っとるだけでは、振り回されて、あかんようになってくわ。もうそろそろ自分たちの手にコントロールを取り戻して、元気でおらんと、あかんわ!!」と、四日市弁ばりばりで友人と話したのが11月でした。 四日市の男女共同参画センター「はもりあ」の受付フロアは、座り心地のよいソファや興味深い図書や資料をそろえ、カウンターには飲み物も提供されています。タッピングタッチ協会は、ここに団体登録しているので、無料でお部屋が使えます。人数も少ない定員にしているので、「こどものへや」というカーペット敷きの、くつろげる部屋で、距離もゆったりと取ってできます。床に座ることもできるし、椅子やソファもあります。
四日市の男女共同参画センター「はもりあ」の受付フロアは、座り心地のよいソファや興味深い図書や資料をそろえ、カウンターには飲み物も提供されています。タッピングタッチ協会は、ここに団体登録しているので、無料でお部屋が使えます。人数も少ない定員にしているので、「こどものへや」というカーペット敷きの、くつろげる部屋で、距離もゆったりと取ってできます。床に座ることもできるし、椅子やソファもあります。


 子育てにとって大切な「あなたはあなたのままでいい」というメッセージと、触れ合って互いにケアし合うことを、より多くの家族にタッピングタッチで伝えて行きたいですね。
子育てにとって大切な「あなたはあなたのままでいい」というメッセージと、触れ合って互いにケアし合うことを、より多くの家族にタッピングタッチで伝えて行きたいですね。 市の公民館から協会への依頼で、
市の公民館から協会への依頼で、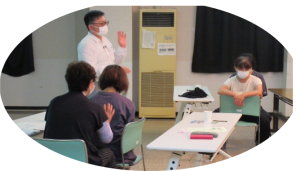 インストラクターである冨森崇さんが、忙しいなか講師を務めてくれました。
インストラクターである冨森崇さんが、忙しいなか講師を務めてくれました。
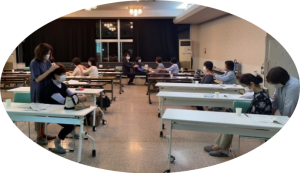 OKね)!もちろん部屋への入退室時には手指消毒と受付時の検温、といった感染予防対策をとって、安心して出来た!ということですね。
OKね)!もちろん部屋への入退室時には手指消毒と受付時の検温、といった感染予防対策をとって、安心して出来た!ということですね。